Linux運用でログ肥大化対策として必ず登場するのが
logrotate の copytruncate(truncate)
ですが、
「とりあえず使う」は非常に危険
です。
本記事では、
- truncateとは何をしているのか
- 使うべきケース
- 絶対に避けるべきケース
- 正しい代替策
を、実務障害事例ベースで解説します。
目次
logrotateの基本動作を整理
logrotateはログファイルに対して以下を行います。
- ローテーション(世代管理)
- 圧縮
- 削除
通常の安全な流れは以下です。
- ログファイルをリネーム
- 新しいログファイルを作成
- アプリに再オープンさせる
これを破壊的に簡略化したのが truncateです。
copytruncate(truncate)とは何か
logrotate設定例:
/var/log/app.log {
daily
rotate 7
copytruncate
}copytruncateは以下を行います。
- ログファイルをコピー
- 元ファイルのサイズを0にする
ファイル自体は削除・リネームされません。
そのため、
ログを書いているプロセスを止めずに回せる
というメリットがあります。
truncateが生まれた理由(背景)
本来、ログローテーションは
アプリがSIGHUPなどでログを再オープンできる
ことが前提です。
しかし現実には、
- 再オープン機能がない
- 再起動できない
- レガシーアプリ
が多く存在します。
その妥協策が truncate です。
truncateを使うべきケース(限定)
① ログ再オープン非対応アプリ
以下の条件をすべて満たす場合のみ許容されます。
- SIGHUP未対応
- 再起動不可
- ログ欠損リスクを許容
② 一時的な応急処置
ディスク逼迫で
「今すぐ空けないと死ぬ」
状況では、暫定措置として有効です。
③ テスト環境・検証環境
本番ではなく、
- ログ精度が重要でない
- 障害影響が小さい
環境では許容されます。
truncateを使ってはいけないケース(重要)
① ログ欠損が致命的なシステム
- 金融
- 監査対象システム
- セキュリティログ
truncateは
コピー中に書かれたログを確実に失います。
② 高頻度ログ出力アプリ
- Webサーバ
- アクセスログ大量出力
この場合、
欠損ログが大量発生
します。
③ マルチプロセス/マルチスレッド
複数プロセスが同時に書き込む場合、
ログ破損・順序崩壊
が発生します。
truncateが引き起こす典型障害
- ログが途中で消える
- 障害解析ができない
- 証跡が残らない
- 監査NG
「容量は空いたが、後で詰む」
典型的な負債系設定です。
正しい代替策(推奨)
① postrotate + SIGHUP
/var/log/app.log {
daily
rotate 7
postrotate
systemctl reload app.service
endscript
}最も正しい方法です。
② アプリのログ再オープン対応
最近のアプリは
- SIGHUP
- USR1
でログを開き直せます。
③ stdout / journald に寄せる
ログファイルを捨て、
- systemd-journald
- ログ集約基盤
に送るのも有効です。
truncateと「削除しても容量が空かない」問題の関係
truncateは
「削除しない」ため、inode問題を回避できます。
しかしこれは、
正しい設計の代替にはなりません。
根本解決は、
- プロセス管理
- ログ再オープン設計
です。
実務判断フローチャート(簡易)
- SIGHUP対応? → YES:truncate不要
- ログ欠損OK? → NO:truncate禁止
- 本番? → YES:慎重に
まとめ
copytruncateは
「便利な裏技」ではなく「最後の手段」
です。
安易に使うと、
- 障害解析不能
- 監査失敗
- 後工程で大事故
につながります。
本記事を、
「truncateを使うか迷った時の判断基準」
として活用してください。
あわせて読みたい

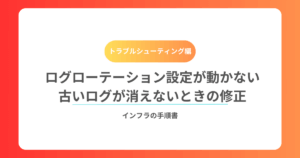
ログローテーション設定(logrotate)が動かない/古いログが消えないときの修正
概要 Linux サーバーではログファイルの肥大化を防ぐために、logrotate による定期的なローテーションが行われます。しかし設定ミスや権限、cron の不具合などにより、…
あわせて読みたい

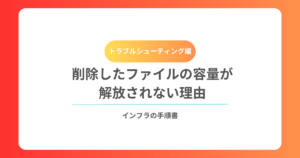
削除したファイルの容量が解放されない理由|dfとduがズレる本当の原因
Linux運用で非常によくあるトラブルが、 「rmでファイルを削除したのに、ディスク容量が空かない」 という現象です。 この問題は、仕組みを理解していないと 無意味なrm…
あわせて読みたい

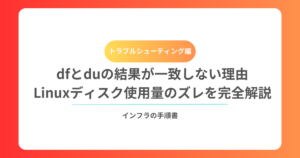
dfとduの結果が一致しない理由|Linuxディスク使用量のズレを完全解説
Linux運用で必ずと言っていいほど遭遇するのが、df と du の結果が合わない問題です。 df -h du -sh / 「dfでは空きがないのに、duではそんなに使っていない」 この状態…
あわせて読みたい


/var/logが肥大化する原因と正しいlogrotate設計
Linuxサーバー運用で頻発するトラブルの一つが、/var/log の肥大化です。 気付いた時にはディスク逼迫、サービス停止、最悪の場合 inode 枯渇に発展します。 本記事では…

